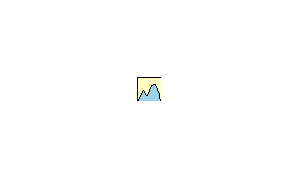| 記録 |
大晦日の夜、初日の出の参拝登山をふと思いつきました。これまでは、キャンプの際に手ごろな山のハイキングなどに連れ出したことはありましたが、それなりの標高の山頂を踏ませたことがありませんでした。我家の子供達もぼちぼちいけそうな年頃なので、大山を選んで初日の出を見に行こうかということになりました。
たまの夜更かしではしゃぐ子供達に提案してみたところ、上の子だけ賛成。 |
大晦日のTV番組を一通り見た後、車で追分のケーブルカー駅へ向かいましたが、駐車場に入る車で大渋滞で身動き出来ず。早々にあきらめ列からはずれ、少し下手の臨時駐車場に入れました。
15分ほど歩いて追分のケーブルカー駅まで登り、下社へ。防寒を万全にし、ヘッドライトをつけて、真っ暗な中急な階段から始まる登山道に入りました。
深夜ですが登山者は多く、抜き抜かれつしながら順調に登ります。山頂にはまだ暗いうちに到着し、日の出に十分間に合いました。 |
真っ暗な下社の登山道入口 |
|
所々大きな石のステップがあり、お尻を押し上げてあげる箇所もありましたが、子供でも全く問題の無い登山道でした。
気温は低く、後で子供に聞かされましたが、汗かきの私の頭は、凍った汗で真っ白だったそうです。
元旦の朝はやや曇り気味で、水平線上にはかなり厚い雲が横たわっていましたが、隙間からきっちり太陽がでてきて一応ご来光を拝むことが出来ました。担ぎ上げた一眼を三脚にセットして、バチャバチャと撮影。 |
雲厚く、初日のちょっと出 |
|
ひとしきり撮影し日も高くなってきた頃、ガスバーナーで湯を沸かしカップラーメンの自炊。傍らの売店ではカップうどんを売っていて、これの香りが極めて芳しく漂ってきて、手ぶらでも良かったかなーとやや後悔しました。
食後一息ついた後、そのままの道で下社まで戻ります。ヤビツ峠への分岐点付近では、きれいな富士山も拝むことが出来ました。
登山道途中の休憩所で一服し、子供は店のおじさんに褒められて、満足の様子でした。 |
元旦の富士山 |
|
神社下社まで降りてきた頃、ちょうどつきたてのお餅の無料配布をやっていて、最後にまたいいおまけが付きました。
厄落としの注連縄をくぐりもう一度参拝し、茶店でまた一息入れた後、ケーブルカーで下山、帰宅しました。 |
くぐって厄落とし、の
阿夫利神社の注連縄 |
|
| メモ |
片道1.5-2時間の、子供でもさほど問題のないルートです。上り口は参道や境内に売店がたくさんあり、また頂上に売店もあって、食べ物関連のおまけの楽しみがあります。
なお登山道自体は平均でそこそこの斜度があり、急傾斜部分には這い上がるほどの大きく複雑な階段状の岩が続く部分も有りますので、注意は必要です。この箇所は、下りではちょっとすべっただけでも怪我をしかねません。
また丹沢によくある木の単調な階段箇所もあり、足腰への負担の掛かる箇所もあります。 |
”丹沢式”の木の階段を下る |
|
ケーブルカーを使って下社まで往復してもいいですが、ケーブルカー部分に男坂(おとこざか)と女坂(おんなざか)という2つの登山ルートが付いていますので、片道1時間弱を足してこれを通ると、ソコソコの運動量を追加できます。女坂途中の大山寺でも初詣できます。ここは、秋にはカエデが絶景になります。
ちなみに有名な大山詣は、江戸時代には大山寺への参拝であったそうです。
現在の下社の位置と頂上に大山寺があったそうですが、明治維新時の廃仏毀釈、神仏混淆廃止の政策により阿夫利神社を分離、大山寺は現在の位置に移転させたそうです。現代日本人は神仏キリストなんでも混淆なので、江戸の人々の感覚に近いんでしょうか?
|